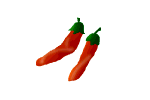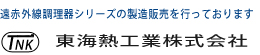「味覚のナゾ」
辛み、これは味ではない。厳密に言うと、私たちの舌にある味細胞で感じる味ではない。痛覚を刺激する味なのだ。
辛みを持つ物質の代表、それはトウガラシである。アメリカ大陸原産の熱帯性植物で、十五-十六世紀の大航海時代にヨーロッパに伝わった。成分はカプサイシンといわれる炭素、水素、酸素、窒素からなる化合物だ。
一般に言われるように、トウガラシなど香辛料は肉の保存に有効なのだが、それにしてもどうして人はあの辛い物質を「おいしい」と思うようになったのだろうか。
カプサイシンを感じ取るたんぱく質(受容体)が、最近見つかった。それは温度に応答するたんぱく質だった。この場所でカプサイシンを受け取ると、人は「熱い」と感じる。
まさしく刺激的な味(?)である。このような刺激を人は好む。これは生物の持つ本能としての好奇心、冒険心ともいえる。ちなみに英語で辛みをホットテイストというのは周知の事実。中国でも、甘味や酸味などの基本となる五味とはまた別の五性という分類で、体を熱くする食べ物として辛みをとらえている。
辛みと並んで不思議な味がうまみだ。
うまみとはグルタミン酸ナトリウムというアミノ酸、そしてイノシン酸ナトリウムやグアニン酸ナトリウムという、遺伝子を作っている成分、核酸系物質の持つ味のことである。
グルタミン酸ナトリウムは1908年、東京大学の池田菊苗(きくなえ)教授が発見し、その味をうまみと命名した。イノシン酸は、かつお節のうまみ成分、グアニル酸はシイタケのうまみ成分である。どちらも日本人の発見による。
グルタミン酸とイノシン酸、グアニル酸には、相乗効果と呼ばれる、お互いに味を強め合う顕著な効果がある。市販のうまみ調味料は二種類のうまみ物質を含み、まさしくこの効果を利用している。うまみの相乗効果は、私たちも日常の料理に取り入れている。
たとえば、日本料理のだしをとる場合、かつお節と昆布の両方を使った方が、飛躍的にうまみが増す。西洋料理でもスープには肉と野菜の両方を使うが、これも肉からのうまみと野菜から出るうまみの相乗効果を利用している。
(九州大学教授 都甲 潔)